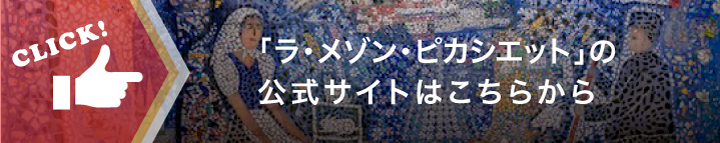これまで《世界のワクワク住宅》では、家のあらゆる調度品が紙で作られた「ペーパーハウス」(アメリカ・ロックポート)や、ビールの空き缶で覆い尽くされた「ビアカンハウス」(アメリカ・ヒューストン)、さらには木製彫刻が際立つ「ユンカーハウス」(ドイツ・レムゴ)など、特定の素材を用いた装飾を施した不思議な家をいくつかご紹介してきた。
芸術然としたコンセプトというよりは、自らが思い描くヴィジョンに導かれ、生涯をかけてコツコツと作り上げられた小宇宙のような家々。家がその主の感性を最大限に具現化するためのこだわりの舞台となる様子は、見ていてとてもワクワクする。
今回は、パリの南西にあるシャルトルの街に立つ、モザイクタイルに覆われた「ピカシエットの家」をご紹介する。色とりどりに煌めく細かなモザイクが、外壁のみならず、家の中の壁、家具などの調度品、庭など、そこかしこに散りばめられている宝石のような家だ。その背景にはどのような物語があるのだろう。

©︎Studio Martino
19世紀が終わろうとする1900年、聖母マリア誕生の祝日に8人兄弟の7人目としてシャルトルで生を受けたレイモン・イシドール(1900-64年)が、この家の主。
子どもの頃は目が不自由だったが、10歳の頃、母親とともにシャルトルのノートルダム大聖堂(以下、シャルトル大聖堂)にいた時に突然視力を取り戻し、初めてステンドグラスを通して色彩を見ることができたという話が残っている。その経験が深い信仰心と芸術への関心を彼の中に芽生えさせた。
その後レイモンは初等教育を終えたのち、13歳で鋳物工として働き始め、20歳頃から占領下のドイツ・ラインラントでフランス軍に従軍した。1924年に結婚したアドリアンヌという女性は彼より11歳年上の未亡人で、結婚当時3人の子どもがいた。彼女は、「3人の子どもを抱えた私を受け入れてくれた」と、レイモンに生涯感謝していたという。

©︎Studio Martino モン・サン・ミッシェルが大きく描かれた食堂。ここから奥へ進むと、森の動物たちやシャルトル大聖堂の遠景などが続く
この新しい家族を守るべく、レイモンは自分たちの住む家を持つことを夢みていた。結婚から数年後、裕福ではなかったものの、彼はようやくシャルトルに小さな土地を購入し、自ら家を建て始めた。1931年に家が完成した頃、レイモンは市の道路作業員として雇われていた。最初はごみ集積所の管理人、その後は道路や小道の維持管理を担当した。仕事で歩き回るうちに、割れたガラスや陶器の煌めきに惹かれ、それらを拾い集めて庭の隅に置くようになったのをきっかけに、彼は家をタイルで装飾するアイディアを思いつく。
長方形の敷地内には、母屋と祈りの間、中庭を挟んだところに「夏の家」という離れがあり、さらに奥には庭がある。最初は母屋の内部の装飾から始まった。レイモンは、床から天井まで家の隅々に絵を描き、彫刻を彫り、モザイクを施した。

©︎Maison Picassiette 妻アドリアンヌのミシンもモザイクが施されている。踏みペダルまでタイルで覆うという徹底ぶり
草花、木々、船、動物、人物。さまざまなモチーフが多色のタイルで丁寧に描かれた。敬虔なクリスチャンであったレイモンは、聖書に登場する人物や象徴的シンボル、エルサレムの街並みや、家からそう遠くない場所にあるシャルトル大聖堂の絵もたくさん描いている。椅子やテーブル、吊り戸棚、ベッド・・・しまいには妻アドリアンヌのミシンまでモザイクで覆ってしまうという始末! そんな様子を目にした彼女は「いつか目覚めたら、あなたにモザイクで覆われてしまっているわ」と笑ったそうだ。

©︎Maison Picassiette
1945年以降、レイモンは外に出て外壁や前庭を飾り始める。そんな彼の姿を目にした近所の人々は、彼の制作の参考にと絵葉書を持ち寄り、子どもたちは割れた食器の破片を手にこの家を訪れるようになった。

©︎La gardienne モザイクのディテールを見ると、サイズの異なるタイルの破片が巧みに組み合わされていることがわかる
人々の注目を集めた彼はやがて「ピカシエット」というあだ名で呼ばれるようになったが、これは「皿泥棒」、つまり「つまみぐいをする」を意味するpiquer l’assietteと、芸術家ピカソの名前をかけた造語である。さまざまな物を拾い集めながら、独自の芸術表現に勤しんだレイモンに向けられた嘲笑と賞賛を同時に表すものだと言えるだろう。

©︎Maison Picassiette モザイクに覆われたストーブ。背景の壁とのコントラストなど、配色の妙もポイントのひとつ
33年という歳月の間に、ゴミ捨て場や道路を何百キロも歩き回り、15トンもの多色のガラスや食器の破片を拾い集めたレイモンの壮大なライフワーク。ひたすら制作に向き合った彼であったが、1964年、65歳になる前日に彼は家から15キロ離れた道端で意識不明の状態で発見される。その後、自宅のベッドで、妻と義理の息子たちに見守られながら永眠し、シャルトル大聖堂を望むサン=シェロン墓地に埋葬された。少しずつ新しい土地を取得し、創作を増やし続けたレイモンであったが、この頃にはモザイクで覆う場所がもう何も残っていなかったそうだ。
彼の活動を生涯支えたアドリアンヌは1979年までこの家に住み続け、1981年にシャルトル市がこの家の所有権を取得した。その後「ラ・メゾン・ピカシエット」は国の歴史的記念物に指定され、現在も博物館として一般公開されている。

©︎Studio Martino 控えめな敷地の一番奥にある庭には細かい光を放つモザイクと呼応するかのように色とりどりの小花が咲き誇っている
パリから電車で一時間ほどの場所にあるピカシエットの家だが、そこを訪れた人は皆、口を揃えて一見の価値がある場所だと言う。たとえば1953年には、20世紀を代表するフランスの著名な写真家、ロベール・ドワノーもここを訪れ、レイモンとアドリアンヌ、そして家の様子をカメラに収めている。しがない清掃員の暮らしぶりが一流の写真家であったドワノーの心を捉えたという話は、レイモンの人柄と芸術について多くのことを示唆しているのではないだろうか。
レイモンが描いた人物の多くはアドリアンヌをモデルとしていると言われている。そうした家族への愛、信仰心、そして自らの芸術的感性に忠実であったレイモンの人生がここ、ピカシエットの家に美しく結実している。
写真/All sources and images courtesy of Maison Picassiette Chartres, C’Chartres Tourisme
取材・文責/text by: 河野晴子/Haruko Kohno